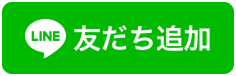不妊症とアルコールの関係について
毎日アルコールを摂取している男性は、精液の量が少なくなり、精子正常形態率が低くなります。女性の場合は、飲酒と不妊症の関係が判明しているわけではありませんが、気づかないうちに妊娠している可能性もあるため控えるべきです。
不妊治療中は、1週間に2日程度、適度な量の飲酒に留めましょう。
アルコールが及ぼす不妊症への影響(男性)
アルコールが男性の生殖機能に与える影響は、それほど大きくありません。
ただし、毎日飲酒をしている場合は影響があるとされ、特に、精液量と精子の正常形態率に問題が出てくると言われています。
アルコールと不妊症の関連性については、イタリアの16,395人の男性を対象に調査が行なわれました。調査の結果を見ると、時々飲酒をする男性に比べて、毎日飲酒をする男性は、精液量が少なくなり、精子の正常形態率が低くなるという結果が報告されたのです。
アルコールが及ぼす不妊症への影響(女性)
女性の場合、アルコールを飲んだほうが妊娠しやすくなるという報告と、アルコールを飲むと妊娠しにくくなるという報告があり、結果は両極端に分かれます。
スウェーデンやデンマークで行なわれた研究によると、アルコールを摂取する日数が多くなればなるほど不妊症になる可能性は高くなり、しかも、年齢が高くなるにつれ、その傾向は顕著に現れると報告されました。
しかし、デンマークでの別の調査によると、全くアルコールを摂取しない女性よりも、適度に摂取する女性のほうが妊娠しやすいという報告もなされています。
ただし、女性は男性と比較して体が小さい分、アルコールの影響を受けやすいことは事実です。また、気づかないうちに妊娠をしていれば、無意識に胎児にアルコールを与えてしまう結果にもなりかねないため、やはり控えるべきでしょう。
飲酒の目安について?
妊娠を望む時の飲酒の目安量は、イギリスのNICE(National Institute for Clinical Excellence)によると、「週に1回から2回までの飲酒で、1回の飲酒量はアルコール16g」までとされています。
アルコール16gを実際のお酒の量に換算してみると、度数5度のビールであれば200~400ml程度となり、度数14~15度のワインや日本酒では144mlまでとなります。
アルコールの多量摂取は、不妊症だけでなく、健康にも悪影響を与えてしまう恐れがあります。1週間のうちに2日まで、適度な量の飲酒を楽しむようにしてください。
不妊症治療中はアルコール摂取を抑えて
アルコールは不妊症に影響を与えるとされており、毎日飲酒をする男性は、時々飲酒をする男性と比較して、精液量が減少し、精子の正常形態率に問題が出てくるとされています。
一方で女性の場合は、アルコールからの影響が判明しているわけではありませんが、気づかないうちに妊娠をしている可能性もあるため、やはり控えるべきです。
不妊治療を行っている時の飲酒は、週に2日まで、適度な量を楽しむ程度に抑えてください。