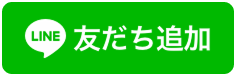2022年4月から不妊治療の保険適用が拡大されました。これにより、体外受精(IVF)や顕微授精(ICSI)などの高度生殖医療も健康保険の対象となり、多くの夫婦にとって経済的負担の軽減が期待されるようになりました。しかし、一方で課題も浮かび上がっています。このコラムでは、不妊治療の保険適用拡大のメリットとデメリットについて詳しく解説します。
1.メリット
①経済的負担の軽減
不妊治療、とりわけ体外受精をはじめとする高度生殖医療は、高額な費用がかかりました。体外受精や顕微授精は1回あたり40〜100万円がかかり、さらに複数回の治療が必要になることも少なくありません。これまでは自治体による助成金制度があったものの、全額自己負担であったため、経済的な理由で治療を断念する夫婦も多くいました
保険適用によって、3割負担で治療を受けることが可能になり、例えば1回40万円の治療費であれば自己負担額は12万円程度となります。これにより、より多くの夫婦が不妊治療にアクセスしやすくなりました。
②治療のハードルが下がる
経済的な負担が減ることで、「費用が高すぎるから不妊治療を諦める」といったケースが減少し、より多くの夫婦が治療を受ける選択肢を持てるようになりました。特に、比較的若い年齢のうちに治療を開始できる可能性が高まり、妊娠率の向上につながっています。
③透明性の向上と標準化
保険適用に伴い、不妊治療の診療報酬体系が明確化され、不妊治療の標準化が進みました。これまではクリニックごとに治療費の設定が異なり、同じ治療でも金額に大きな差がありましたが、保険適用によって一定の基準が設けられました。
また、保険適用されたことにより、治療内容がより厳しく審査されるようになり、科学的根拠に基づいた適切な治療(EBM)が推奨されるようになりました。
④社会的な理解の促進
不妊治療の保険適用が拡大されたことで、国として不妊治療を支援する姿勢が明確になり、社会的な理解も深まりつつあります。不妊治療を受けることが「特別なこと」ではなくなり、仕事との両立を支援する企業も増えてきています。
2.デメリット
①保険適用の範囲が限定的
保険適用されたとはいえ、すべての不妊治療が自由に受けられるわけではありません。例えば、保険適用の対象となるのは一定の年齢(43歳未満)までであり、それ以上の年齢では自費診療となります。また、1回あたりの移植回数の制限(40歳未満は6回、40歳以上は3回)もあり、保険適用外となるケースも少なくありません。
さらに、着床前診断(PGT-A)や最新の治療技術などは保険適用外となり、最先端の治療を希望する場合は高額な自己負担が発生します。
②自由診療の選択肢が減少
保険適用が拡大されたことで、多くの医療機関が保険診療の範囲内で治療を行うようになりました。その結果、従来の自由診療で提供されていた柔軟な治療が受けにくくなっています。例えば、これまでクリニック独自の方法で行われていた個別対応の治療が、保険診療の枠組みに制限され、画一的な治療になりがちです。
また、保険診療の治療制限を理由に、自由診療へ誘導するクリニックも増えてきています。
③医療機関の負担増加
保険適用により患者数が増加したことで、一部の不妊治療クリニックでは予約が取りにくくなり、治療を希望しても長期間待たされるケースが増えています。また、医療機関側は、保険診療の枠組みに沿った治療計画を立てる必要があり、これまで自由診療で柔軟に対応していた治療法が制限されることになりました。
④医師の診療方針が変わる可能性
保険診療には診療報酬の制約があり、医療機関側は一定の治療内容に基づいた診療を行わなければなりません。そのため、患者ごとに最適なオーダーメイド治療を提供するのが難しくなっています。
例えば、本来であれば特定のホルモン療法や追加の検査が必要なケースでも、保険適用範囲内で治療を進める必要があるため、結果的に妊娠率が下がる可能性があります。
さいごに
不妊治療の保険適用拡大は、多くのカップルにとって経済的負担の軽減や治療のハードル低下といった大きなメリットをもたらしました。特に、若年層が早い段階で治療を受けられるようになったことや、標準化による透明性の向上は大きな前進と言えます。
一方で、保険適用の制約により、自由診療の選択肢が狭まったり、医療機関の負担が増えるというデメリットもあります。また、最新の治療法が適用外となることがあるため、すべての患者にとって最適な制度とは言い切れません。
体外受精は不妊治療の最終段階に位置する医療であり、簡単に考えるべき医療ではありません。ところが保険適用の拡大以降、不妊治療=体外受精の様相を呈しており、私は憂慮しています。大切なことは、それぞれのカップルが、自分たちがイニシアティブをもって、最適な治療を選択することであり、そのためにはリテラシーが必要です。「不妊ルーム」では、そのお手伝いをしています。