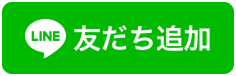- TOP
- 「妊娠しやすいカラダ」インタビュー
- 「不妊ルーム」はこう考えます
「不妊ルーム」はこう考えます
- 聞き手:
-
先生の考えは?
- 放生:
-
「不妊ルーム」はどう考えるのかというと、しばらくフォローしてから子宮卵管造影検査を依頼します。本に書いた通り、不妊の先生は、ルーチンで最初の方で子宮卵管造影検査をやるけれど、僕の考え方は少し違っている。僕は、最初にやるのはどうかと思っている。むしろ、この検査をやったあと、妊娠しやすくなるという事実があるので、妊娠しやすいタイミングにやった方がいいと思うのです。ですから僕は、この人そろそろいいかなあと思ったら、紹介状を書いて卵管造影検査をしてもらいます。
- 聞き手:
-
本もありますね。そのくだりが。
- 放生:
-
だから、僕は思うのですが、とにかく不妊治療をやろうと思ったら、精液検査ができるかということと、子宮卵管造影の設備があるかどうかを確認すること。そして、医者を選ぶポイントとしては、基礎体温表を丁寧にみてくれるかどうかです。僕はこの3つを重要と考えている。
- 聞き手:
-
そうですよね。
- 放生:
-
検査はいくらでもあげられると思いますが、大切なのは、その3つだと僕は思います。要するにこれからの時代は、患者側がリテラシーを持たなくてはいけないと、僕は思います。不妊治療を選択するリテラシーを持たなくてはいけない。「不妊ルーム」には二本柱みたいなものがあって、一つは「不妊ルーム」で妊娠が期待できそうと思う人を、半年間を目途にフォローしてみる。その流れで妊娠したらハッピー。妊娠しなかったら、今度は僕の今までの経験から、その人にあった信頼できる先生を紹介するというのが一つの柱なんです。
もう一つの柱というのは、あきらかに不妊治療が必要な、先程と重複しますが、僕がセカンドオピニオンを述べて、今の治療でいいのか、あるいはこうした方がいいというアドバイスをする。僕自身がいっていることは、正直なところ人間が人間に対応しているのだから、僕が100%正しいとはもちろん思っていないし、僕のアドバイスに不満を持つ人も当然いるだろうと思います。