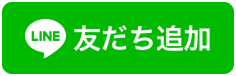仕事と妊活のはざまで
女性の社会進出が進み、今やあらゆる分野で女性の力が欠かせなくなっています。
「この部署は女性でなければ回らない」
そう感じている会社も少なくありません。
実際、ある出版社の著名な女性編集長は、こんな本音を語ってくれました。
「採用試験をすると、筆記でも面接でも、上位はほとんど女性なんです。これでは男性が入社できないので、“調整採用”をしているのが実情です」
優秀な女性たちが社会で活躍している一方で、その陰で「結婚」「妊活」のスタートが遅れがちになっていることも否めません。
気がつけば30代後半、周囲が出産ラッシュを迎える中で、ようやく妊娠について真剣に考え始める…。
これは珍しいことではなく、むしろ今の日本では“ごく普通の姿”になりつつあります。
不妊治療で失うもの
しかし、社会で活躍する女性がいざ不妊治療に取り組もうとすると、そこには大きな壁が立ちはだかります。
時間、体力、そしてお金。
特に体外受精に進めば、その負担は想像を超えます。
排卵誘発の注射を繰り返し、卵胞の計測、そして採卵のために何度も通院し、移植のスケジュールに振り回される…。
それらは、「会社員としての時間」も「母としての時間」も、削ってしまいがちです。
そして怖いのは、一度体外受精にエントリーしてしまうと、なかなか抜け出せなくなること。
「ここまでやったのだから、もう一回だけ」
「次こそはうまくいくかもしれない」
まさにギャンブルに負けがこんで、次で取り返そうという射幸心と同じ。
そんな気持ちが背中を押し、気がつけば心も体も疲れ果ててしまう…。
これは決して珍しいケースではありません。
Wさん(38歳)のケース
そんな現実を象徴するようなエピソードを、ある妊活女性が教えてくれました。
Wさん、38歳。
第一子は自然妊娠で授かり、子どもがよちよち歩きを始めた頃、二人目を望むようになりました。
自分たちでタイミングを見ながら妊活を続けましたが、なかなか授からず。不安を抱えながら不妊治療のドアを叩きました。
医師から言われたのは、「37歳を過ぎていますから、体外受精に早めに進むべきです」という言葉。
Wさんはその言葉に従い、採卵、そして移植へと進みました。結果は、妊娠には至りませんでした。
そして、Wさんは「不妊ルーム」に相談に来られました。
彼女が口にした言葉は、私の心に強く残っています。
「体外受精という医療を経験してわかったのは、想像を遥かに超えて、時間的な制約が大きいことでした。私は仕事をしています。とてもじゃないけど、こんな治療を2回、3回と続けることはできません。子育てもありますし、本当に大変な重労働でした。妊娠しなくてもかまいません。先生のところでフォローアップしていただければ、それで十分です」
彼女の瞳には、安堵と涙が入り混じっていました。
「頑張らないと」と走り続けてきた人が、ようやく肩の荷を降ろせた瞬間だったのかもしれません。
本当の意味での「賢明な選択」
体外受精の大変さは、時間的制約だけではありません。
強い薬を繰り返し注射することによる肉体的負担、費用が膨れ上がる経済的負担、そして結果が出なかったときに襲ってくる精神的ダメージ…。
「想像を絶する」と表現した彼女の言葉は、決して大げさではありません。
むしろ、それを正直に語れる人は少数派です。
多くの人は治療の波に飲み込まれ、「やめられないネガティブ・スパイラル」状況に追い込まれていきます。
しかしWさんは、自分の人生を見据え、「ここで立ち止まる」という勇気ある選択をしました。
それは「諦め」ではなく、「賢明な選択」です。
自分にとっての「幸せ」を見つめ直す
私は「不妊ルーム」での経験から常々思います。
不妊治療だけが妊娠に至る道ではない、と。
もちろん、医療の力で子どもを授かることはひとつの方法です。
けれども、子どもができなかったとしても、それまでのプロセスは無駄ではありません。
働く女性にとって不妊治療は、「自分のキャリア」と「家庭」と「未来」を揺るがすことがしばしばです。
だからこそ、どこかで立ち止まり、深呼吸し、自分にとっての「幸せ」を見つめ直すことが必要だと思うのです。
必死に妊活を頑張るあまり、自分を追い詰めるのはやめましょう。
妊活の神様は、あまのじゃくです。
「妊娠は追いかけると逃げて行き、忘れた頃にやってきます」