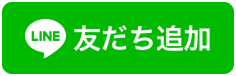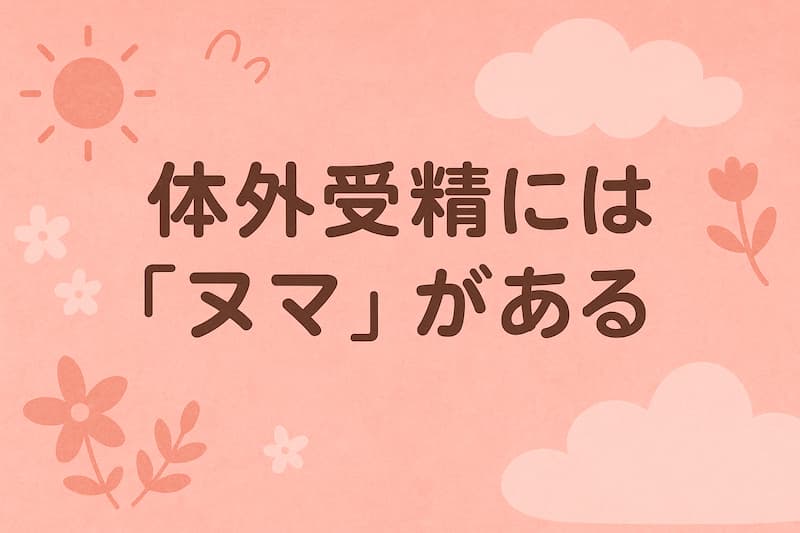先日、このホームページのコラムで「人工授精の壁」について書いたところ、多くの反響をいただきました。
「まさに私のことだと思いました」「涙が出ました」——そんな声を頂戴しました。
そして今日は、その先にある大きな難所についてお話ししたいと思います。
それが「体外受精の〝ヌマ〟」です。人工授精に「壁」があるとするならば、体外受精には「ヌマ」がある。ヌマとは、はまってしまうと抜け出すことができない場所。がんばってもがけばもがくほど、深みに落ちていく場所。治療を受けておられる方なら、この言葉に胸の奥がざわつくのではないでしょうか。
39歳Aさんの3年半
たとえば、39歳のAさん。タイミング法のあと人工授精を飛ばし、体外受精に挑戦しました。勇気をふりしぼり、期待を胸に、治療を始めたのです
けれども現実は厳しく、8回の採卵のうち、移植にまでたどりつけたのは、たった1回。その間に費やした時間は2年余り。かかった医療費は400万円を超えていました。お金だけではありません。体調を崩すほどの副作用、毎回の通院、注射、採卵の痛み、そして「またダメだった」という絶望。Aさんは、心も体も、ヌマの底に沈み込んでいくような日々を過ごしていました。
そんな中で「不妊ルーム」に相談に来られたのです。「もう後戻りできない」「でも、結果が出ない」——その狭間で苦しみ続けていました。私は彼女の「母になりたい」という強い思いを尊重しつつ、別の選択肢を提示しました。私が信頼している高度生殖医療のクリニックをご紹介したのです。
6キロの距離と3年半の時間
紹介先でAさんは、1度の体外受精、1回の移植で妊娠。そして、念願の母となりました。
その後、彼女から届いたメールにはこう綴られていました。
「私が長らく通っていたクリニックと、先生が紹介してくださったクリニックは、わずか6キロしか離れていません。でも、その6キロを埋めるのに3年半かかりました。先生と出会っていなければ、この距離は永遠に埋まらなかったと思います。」
私はその文面を読んで、胸が熱くなりました。6キロという距離。地図で見れば、電車で10分もかからない距離です。でも、不妊治療においては、その6キロが「絶望と希望」を分けるほどの隔たりになる。ヌマから抜け出すきっかけがあるかどうかで、人生が大きく変わってしまうのです。
なぜヌマにはまるのか
体外受精は、医療の中でも高度で複雑な治療です。だからこそ、医師の技術や方針、設備、検査体制の違いが、そのまま結果に直結します。
しかし、患者さんの側からは、その違いは見えにくい。
「きっと次はうまくいくはず」
「先生が言うのだから」
「もうここまで来たのだから、やめられない」
そう思いながら、気づけば深みに沈み、抜け出せなくなってしまうのです。これが体外受精のヌマの正体です。
セカンドオピニオンというロープ
ヌマから這い出るために必要なのは、「セカンドオピニオン」です。これは、今通っている病院を否定するためのものではありません。別の視点を取り入れ、違う道筋を照らすための大切な一歩です。
Aさんにとって、そのロープは「6キロ先のクリニック」でした。でも、どんな方にとっても「別の視点」は、きっと自分を助ける大切なきっかけになるはずです。
私は「不妊ルーム」で数多くの患者さんに接してきましたが、セカンドオピニオンで人生が変わる瞬間を何度も見てきました。治療そのものが変わることもあれば、治療との向き合い方が変わることもあります。いずれにしても、ヌマから這い出すきっかけを得るのです。
エントリーの前に相談してほしい
私はいつも、強調してもしすぎることはないと思っていることがあります。
それは「体外受精にエントリーする前に、まず相談に来てほしい」ということです。治療は、始めてしまうと止めづらい。だからこそ、始める前に、選択肢や可能性を一緒に考えることが大切です。その一歩が、あなたの未来を変えるのです。
あなたへ
もし今、このコラムを読んでくださっているあなたが、体外受精のヌマに沈みそうになっているなら——どうか、一度立ち止まってください。あなたの努力や時間や涙は、決して無駄ではありません。でも、その努力を結果につなげるために、別の視点が必要になることがあります。
一人でヌマでもがかなくていいのです。一緒に考えましょう。そのために「不妊ルーム」があります。
どうか、あなたの未来が光で照らされますように。「不妊ルーム」はお役に立ちたいと思います。