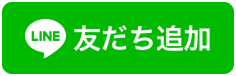冷え性と一相性の基礎体温表
Mさんは、「不妊ルーム」でも特に印象に残っている方のひとりです。
初診のとき、彼女は開口一番こう話されました。
「子どもがほしいのも事実ですが、それよりもこの冷え性をなんとかしたいんです。
もう何年も基礎体温をつけていますが、36.4℃を超えることなんて、めったにないんです」
その言葉の通り、彼女が持参された基礎体温表は、見事に“平ら”でした。
通常なら低温期と高温期に分かれるはずの体温が、一相性でほとんど変化がありません。
これは、排卵が起こっていない「無排卵」を示す典型的なパターンです。
さらに、生理中のホルモン検査を行うと、黄体形成ホルモン(LH)が卵胞刺激ホルモン(FSH)よりも高く、通常とは逆の結果でした。
このような状態は、多のう胞性卵巣症候群(PCOS)など、排卵障害をともなう状態でよく見られます。
Mさんの主訴は「冷え」でしたが、その背景には明らかにホルモンバランスの乱れがありました。
当帰芍薬散で体が動き出した
そこで、私はMさんに「当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)」という漢方薬を処方しました。
この薬は、体をあたためながら血流を整え、女性ホルモンの働きを助けるといわれる処方です。
特に、冷え性で貧血気味、月経周期が不安定なタイプの方によく合います。
服用を始めてからしばらくして、Mさんの基礎体温に変化が現れました。
それまで平坦だった体温表に、低温期と高温期のリズムが生まれたのです。
つまり、排卵が起こるようになったということです。
さらに驚いたのは、ホルモンの数値です。
検査ではFSHがLHを上回り、まさに「教科書通り」の正常パターンへと改善していました。
体が本来のリズムを取り戻し始めたのです。
そして次の周期、弱いながらも妊娠反応が陽性に。
惜しくもその後すぐに生理が来てしまい、初期流産という結果にはなりました。
しかし、この出来事は「体が再び妊娠できる力を取り戻した」ことを示していました。
ステップアップか、もう少し漢方薬で続けるか
その後も基礎体温は二相性を保ち、月経周期も安定していました。
ところが、なかなか次の「コウノトリ」がやってきません。
半年ほどフォローアップを続けたころ、私は彼女にこう提案しました。
「ここまでホルモンバランスも整ってきたので、次の段階として不妊治療へのステップアップを考えてみてはどうですか?」
けれども、Mさんにも事情がありました。
彼女はIT関連企業で働くシステムエンジニアで、仕事が非常に多忙。
外来にはいつも診療終了ギリギリに駆け込むように来られていました。
「先生、ここに通えなくなることは、治療をやめるのと同じなんです。
もう少しだけ、先生に診てもらいながら続けたいんです」
そう言われてしまっては、私も背中を押すことはできません。
そこで、もう少し漢方薬でのフォローアップを続けることにしました。
温経湯が“仕上げ”となった
季節が変わり、冷え込みが厳しくなってきたころ。
私はMさんの体の状態を見て、漢方薬を「温経湯(うんけいとう)」に切り替えることにしました。
温経湯は、冷えの強いタイプの方に使われる代表的な処方です。
血のめぐりを良くしながら、女性ホルモンの分泌をさらに整える作用があります。
この切り替えが、まさに“劇的な変化”のきっかけになりました。
服用を始めてからしばらくして、再び妊娠反応が陽性となったのです。
産婦人科での診察でも、胎嚢(たいのう)が確認され、正式に妊娠成立。
彼女の努力が、ようやく報われたのでした。
最初にMさんが来院してから、実に1年2か月が経過していました。
決して短い道のりではありません。
その間に彼女は、体の冷えを克服し、自分のリズムを取り戻しました。
そして心のバランスまでも整えていったのです。
「体が整う」と「心も整う」
Mさんが最後に語ってくれた言葉が、今でも印象に残っています。
「最初は“妊娠するための治療”だと思っていたけれど、途中から“自分の体と心を整える時間”になっていました」
妊活というと、どうしても結果を急ぎたくなります。
けれども、Mさんのように、まず「冷え」や「ホルモンバランス」といった“土台”を整えることが、遠回りに見えて、実は妊娠への道であることも多いのです。
漢方薬は、単に薬で体を動かすものではありません。
体の声を少しずつ聴きながら、本来のリズムを取り戻す“伴走薬”のような存在です。
そして、その変化を信じて丁寧に続けることが、未来の命への第一歩になるのだと思います。
Mさんのケースは、まさに「漢方が劇的に効いた」例でした。
その背景には、彼女自身の粘り強さと、心身を見つめ直す姿勢がありました。
治療の中で「体の温かさ」と「心の温かさ」が重なったとき、人は本来のチカラを取り戻していく。
改めて感じさせられた症例でした。