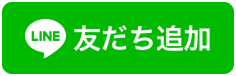情報の時代がもたらした“安心”と“混乱”
今や、妊活や不妊治療について調べようと思えば、スマートフォンひとつで膨大な情報が手に入ります。
検索すれば「排卵日」「タイミング法」「AMH」「体外受精」など、あらゆるキーワードに関連した記事や動画が並びます。
そして、その中には「妊娠するにはこの方法しかない」「40代での自然妊娠は奇跡」といった、読んでいる人を不安にするような内容も少なくありません。
こうした“情報の洪水”が生み出した新しい落とし穴を、私は「インターネット不妊」と呼んでいます。
そして近年、さらに厄介なのが、その進化形とも言える「SNS不妊」です。
「インターネット不妊」とは何か
インターネットの登場によって、不妊に関する情報は一気にオープンになりました。
以前は、病院で医師の話を聞くか、実用書を読むしか得られなかった情報が、誰でも簡単に手に入るようになったのです。
また、患者さん自身が自分の体験をホームページやブログで発信するようになり、「治療の実際」や「通院の雰囲気」をリアルに感じ取れるようになりました。
こうした動きは、当時としては画期的でした。
人に相談しづらいテーマだからこそ、匿名で情報交換できる場は多くの人に支持されたのです。
一方で、便利になりすぎたがゆえに、情報を集めすぎて頭がいっぱいになり、かえって混乱してしまうケースも出てきました。
検索を続けるうちに「何が正しいのかわからない」「私はどれに当てはまるの?」と迷い、どんどん不安が膨らんでいく。
インターネットのリンクは、永遠に終わりのないドアを開け続けることになりかねないのです。
これが「インターネット不妊」です。
そして、時代は「SNS不妊」へ
しかし今、より深刻なのは「SNS不妊」です。
SNSの特徴は、アルゴリズムが“あなたの関心”に合わせて情報を自動的に選び、繰り返し似た投稿を見せてくること。
一度「妊活」や「不妊治療」に興味を持って検索や閲覧をすると、その後は関連する投稿が次々と表示されます。
最初は「参考になる」と感じていても、次第にタイムラインが不妊関連の情報一色になり、「治療しないと妊娠できない」「みんな頑張っているのに私は遅れている」と焦りを感じるようになる人が少なくありません。
まるで、情報のトラップにかかったように、抜け出せなくなってしまうのです。
そしてSNSでは、「このサプリで妊娠しました」「○○クリニックで奇跡が起きました」といった個人の体験談が、強い共感とともに拡散されます。
それらが真実かどうか、どんな背景があるかはわかりません。
けれど、“リアルな声”として響くため説得力をもって心に入り込んでしまうのです。
この結果、SNSを通じて偏った情報を信じ込んでしまい、「自分流の不妊理論」を作り上げてしまう人も少なくありません。
いわば“SNS不妊博士”が次々と誕生しているのです。
なぜSNS情報は危険なのか
SNS情報の最大の問題点は、“検証されていない”ことです。
医療機関の公式サイトであれば、責任があります。
しかし、SNSは基本的に誰でも自由に発信できる場です。
そこでは誤った知識や極端な意見も、あたかも正しい事実のように拡散されてしまいます。
また、アルゴリズムの仕組みによって、異なる意見や対立する情報が目に入りにくくなる点も見逃せません。
自分の見ている世界が“真実のすべて”のように感じてしまうのです。
その結果、「自然妊娠はもう無理」「私も早く体外受精をしなければ」といった思い込みが生まれ、本来の体や心のリズムを乱してしまうことがあります。
つまり、「SNS不妊」は、情報の過剰摂取によって生まれる“心のストレス不妊”とも言えるのです。
では、どうすればいいのか?
まず大切なのは、「情報を選ぶ目」を持つことです。
ネット検索やSNSを見る前に、「私は何を知りたいのか」「今、必要な情報はどんなことか」を一度立ち止まって考えてみてください。
これが「SNSリテラシー」です。
そして、いきなり医療機関の公式サイトや広告ページに飛びつくよりも、信頼できる体験者が運営するコミュニティや、専門家が関与しているサイトを参考にする方が安心です。
医療機関のサイトにはどうしても宣伝的な意図が含まれることもあるからです。
また、「複数の視点をもつ」ことも大切です。
ひとつの投稿、一冊の本、一人の意見にしがみつくのではなく、違う立場の話も聞いてみる。
その上で、自分の体験や価値観に合ったものを選んでいく姿勢が必要です。
最後に──情報との「距離感」を大切に
妊活は、情報戦のように見える時代になりました。
けれど、妊娠や出産は“データ”や“理論”だけで説明できるものではありません。
体のコンディション、心のゆとり、夫婦のコミュニケーション、そして偶然やタイミングが重なって、初めて命は宿ります。
だからこそ、情報に支配されるのではなく、情報と“いい距離”を保つことが大切です。
SNSを眺めて不安が強くなるなら、少し離れてみる勇気も必要です。
そして、わからないことや不安なことは、画面の向こうではなく、あなたの体を診てくれるドクターに直接相談してください。
情報はあなたを助けることもあります。
けれど、入手方法を誤れば、あなたの希望を曇らせる“毒”にもなります。
「SNS不妊」に陥らないために──
情報を味方につけ、あなたらしい妊活を歩んでいきましょう。