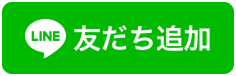不妊治療を始めると、最初のステップで「ホルモン検査をしましょう」と言われることがよくあります。その中でも大切とされているのが「生理3日目」のホルモン値のチェック。これは、妊娠に向けて体がどんな状態なのかを知るための、いわば“体からのメッセージ”を読み取るようなものです。
生理が始まってから2〜4日目くらいに、血液を採って調べるのが一般的です。このときに測るのが、「LH(黄体形成ホルモン)」「FSH(卵胞刺激ホルモン)」「E2(エストラジオール)」「P4(プロゲステロン)」という4つのホルモン。それぞれにちゃんと役割があって、妊娠の準備がうまくいくかどうかに関係しているのです。
では、それぞれのホルモンがどんな働きをしているのか、やさしく説明していきます。
FSH(卵胞刺激ホルモン)
→ 卵巣の元気度チェック!
FSHは、脳の下垂体から分泌されるホルモンで、卵巣に「そろそろ卵を育ててね〜」と指令を出す役割があります。この値が高いと、卵巣がちょっと元気がないかも…というサイン。年齢とともに上がりやすくなるので、卵巣の機能がどの程度保たれているかの目安になります。
理想は10以下くらいです。これを超えてくると、卵子の残りの数が少なくなっていたり、質に影響があることも。もちろん、これだけで判断できるわけじゃないですが、ひとつの参考になります。極端に低い場合も、ホルモン分泌の異常や視床下部の機能低下が疑われます。
LH(黄体形成ホルモン)
→ 排卵をうながすホルモン。バランスが大事!
LHもまた下垂体から分泌されるホルモンで、排卵のスイッチを押すような役割をしています。ただ、生理3日目にこの数値が高すぎると、ちょっと注意が必要です。
たとえば、LHがFSHよりも高くなっている場合、「多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)」の可能性もあります。この体質の人は、排卵がうまくいかなかったり、月経周期が不安定になったりしがちです。LHが高値であることが継続的に認められる場合は、排卵誘発方法の選択に影響を与えるため、治療方針の判断材料になります。
E2(エストラジオール)
→ 卵胞の成熟具合を見るサイン!
E2は、育ってきた卵胞から出てくる女性ホルモン(エストロゲン)の一種で、子宮内膜をふかふかにする働きがあります。数値が高すぎると、「もう卵胞が育ちすぎてるかも?」ということもあって、FSHの値が正しく評価できなくなる場合もあります。
生理3日目なら、E2はだいたい50pg/ml以下が望ましいと言われています。それを超えると、「隠れ卵巣機能低下」や、「ホルモンバランスの乱れ」の可能性を考えることもあります。適切な値であれば、卵胞が順調に発育し始めていることを示します。しかし、数字だけにとらわれず、全体のバランスを見ることが大切です。
P4(プロゲステロン)
→ 排卵してないことの確認用!
P4は本来、排卵が起きたあとに出てくるホルモンで、子宮内膜を妊娠に適した状態に維持する役割があります。ですから、生理3日目には基本的に低くあるべきなのです。この時期にP4が高いと、「もう排卵してた?」とか「排卵しないまま出血が始まってる?」というケースも考えられます。
治療のタイミングにも関わってくるので、P4の値が高かった場合は、次の周期での再検査をすすめられることもあります。
ホルモン値は「あなたの今」を教えてくれるヒント
これらのホルモンは、それぞれ単独で意味を持つだけでなく、大切なのはバランスです。例えば、FSHが正常でもE2が高ければ「見かけ上の正常」である可能性があり、LHとFSHの比が崩れていれば排卵異常のヒントになります。
「数値がどうだった…」と一喜一憂してしまう気持ち、よくわかります。でも、ホルモンの値はあくまで“今の体の状態”を教えてくれる手がかり。怖がらずに向き合って、自分の体をもっとよく知っていくことが、これからの治療や妊娠への一歩になります。
わからないことは、遠慮せずに医師に質問してOKです。不妊治療は、知れば知るほど「なるほど」が増えていく道のりでもあるので、少しずつ一緒に理解を深めていきましょう。