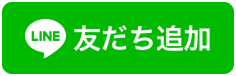保険適用から3年半——何が変わったのか
2022年4月、不妊治療に保険が適用されるという大きな改革が行われました。それから3年半が経過し、世の中はどう変わったのでしょうか?
まず一番大きな変化は、不妊治療がとても身近な存在になったということです。これまでは「経済的に余裕がある人しか受けられない特別な医療」と考えられていたものが、ぐっとハードルの低いものになりました。
これは大変良いことでもあります。これまで経済的な理由で諦めざるを得なかったご夫婦が、一歩を踏み出せるようになったのですから。しかし一方で、その“気軽さ”が新たな問題を生んでいるのも事実です。
「安易な不妊治療エントリー」という落とし穴
保険適用で治療費が下がったことで、妊娠力が十分にある方まで「とりあえず不妊治療を受けよう」と考えてしまうケースが増えています。実際にはタイミングや生活習慣の工夫だけで自然に妊娠できる可能性があるにもかかわらず、最初から医療に頼ってしまうのです。
もちろん「早く子どもが欲しい」という気持ちは自然なことですし、治療を否定するつもりはありません。ただ、本来の妊娠力を信じる前に治療に依存してしまうと、ご夫婦の心と体に必要以上の負担をかけることにもなりかねません。
体外受精のレッドオーシャン化
保険適用拡大の一番の改革は、体外受精(IVF)までが保険適用となったことです。これはこれまでの不妊治療の流れで画期的な出来事でしたが、その副作用も見過ごせません。
東京をはじめとする大都市圏では、「不妊治療=体外受精」という流れが加速しました。おのおののクリニックが患者さんを集めるため、体外受精を積極的に勧めるようになり、まるでレッドオーシャンのように競争が激化しています。
その結果、本来はステップアップ治療の最終段階の体外受精が、最初から提示されるケースも少なくありません。「自然妊娠の可能性をきちんと見極めたうえで進む」という大切なプロセスが飛ばされてしまっているのです。
医療機関の経営事情と患者への影響
この背景には、診療報酬の問題があります。自由診療の時代に比べ、保険診療での報酬は低く設定されています。クリニックにとっては、患者さんの数を増やし、かつ体外受精の件数をこなさなければ、自由診療の時と同じように立ちゆかない事情があるのです。
結果として、「患者さんの妊娠力をどう引き出すか」よりも「いかに効率よく体外受精に誘導するか」が優先されてしまう傾向があります。もちろん、すべての医療機関がそうだというわけではありません。しかし構造的にその流れが強まっているのは否めない現実です。
自分たちが主導権を持つということ
だからこそ、これから妊活に臨むご夫婦にぜひお伝えしたいのは、「不妊治療に受け身で入らない」ということです。大切なのは、自分たちが主導権を握ること。「治療を受けさせてもらう」という感覚ではなく、「治療を利用する」という意識が必要です。
- 自分たちの妊娠力を正しく知ること
- 生活習慣や夫婦のリズムをくずさないこと
- 医師に質問をし、納得しながら治療を進めること
- 基礎体温表をつけながら治療を続けること
こうした姿勢を持つだけで、不妊治療の受け方はまったく変わってきます。
妊活は「治療」だけではない
ここで強調したいのは、妊活は「医療機関に通うこと」だけではないということです。十分な睡眠、バランスの良い食事、ストレスの軽減、夫婦のコミュニケーション——これらが土台となってこそ、治療の効果が最大限に発揮されます。
治療に頼りきりになると、こうした生活の基盤が置き去りになってしまう危険があります。保険適用で治療が受けやすくなった今だからこそ、「自分たちの妊娠力をどう高めていくか」という視点を忘れてはいけません。
主体的に治療を“選ぶ”時代へ
不妊治療の保険適用は、多くのご夫婦にとって希望の光となりました。しかし、その裏側には、安易な治療依存や体外受精偏重、医療機関の経営事情といった現実があります。
これから妊活を進めるうえで大切なのは、受け身にならず、自分たちが主体的に治療を選び取ることです。「どんな治療をするか」よりも、「どう妊娠力を引き出すか」を一緒に考えましょう。
保険適用の時代だからこそ、ご夫婦自身が主役となる妊活が求められています。「不妊ルーム」は、“ふたりの歩みを支える部屋”でありたいと思っています。