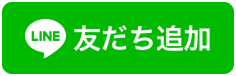診察室で感じた小さな違和感
ある日の診察室。
椅子に座った30代の女性は、少し緊張した様子で私と向き合いました。
しかし最初に出てきた言葉に私は驚きました。
「子どもが欲しいので、体外受精の医療機関の紹介をお願いします」。
私は一瞬、返答を探しました。
「タイミングをとった妊活はしましたか?」と尋ねると、「今は体外受精ですよね。私のまわりも体外受精で授かった女性がたくさんいます」。
迷いはまったくありませんでした。
そのやり取りのあと、私の頭の中に、「不妊治療が、コンビニ化している」というフレーズが浮かびました。
必要なものを必要な時に利用する、そんな感覚で医療が使われ始めている。
それは便利である一方、どこか大切なものが落ちているように感じました。
20年前の予測を越えて
私は2002年に出版した拙著『妊娠レッスン』(主婦と生活社)の中でこう書きました。
-
「今、生まれてくる子どもの100人に1人が体外受精児と言われています。
近い将来、小学校のどのクラスにも1人は体外受精児がいるかもしれません」
当時は未来予測でした。
しかし今、現実は当時の予測を大きく上回っています。
最新のデータでは、2023年に生まれた赤ちゃんの9人に1人が体外受精児です。
体外受精による出生数は8万5048人と過去最多です。
これは単なる医療技術の進歩ではなく、社会における「妊娠」に対する考え方が、大きく変わったのだと言えるのではないでしょうか。
彼女の言葉は象徴的です。
保険適用という「追い風」が生んだ流れ
2022年4月、不妊治療の保険適用が拡大されました。
費用のハードルが下がり、体外受精は以前より身近な選択肢になりました。
しかしその結果、本来の順序がおかしくなり始めています。
従来は「自然に授からないから不妊治療へ」でしたが、今は「子どもが欲しいから治療へ」。
治療が当たり前になればなるほど、「治療すれば授かれる」という想いが生まれます。
そしてうまくいかない時には、その落差はさらに深くなります。
置き去りにされる気持ち
便利さの裏側で、感情が置き去りになる場面が増えていると感じます。
不安、期待、焦り、夫婦間の温度差…。
本来はゆっくり向き合っていくはずの心の動きが、治療のスピードに追いつけないことがあるのです。
“事務的な妊娠”は増えましたが、“心がついていく妊娠”は減っているのでは?
焦らなくていい、深呼吸を!
もし今、治療を始めようとしている方、あるいは迷っている方がいるなら、どうかこう考えてください。
治療は義務ではありません。
周りと比べなくていい。あなたのペースでいい。
大切なのは、納得しながら歩けているかどうかです。
医療が便利になった今だからこそ、「不妊ルーム」の役割は、「選択のアドバイスをすること」、そして「選択したら伴走すること」です。
そして思うのです。
医療の選択の結果ではなく、夫婦が積み重ねた時間と温度をまとって子どもが迎えられてほしいと。
彼女は笑顔で家路につきました
先ほどの女性の話に戻りましょう。
体外受精を当然の選択肢のように話していた彼女に、私は妊娠の仕組みから始めて、体づくり、自然妊娠の可能性が十分あることなどを丁寧に伝えました。
すると彼女はふっと表情をゆるめこう言いました。
「そうですよね。今日からできることがあるんですね。先生に相談してよかったです」。
その笑顔は「治療そのもの」ではなく、「選択肢を理解できた安心」から生まれたものでしょう。
私は改めて、妊活、不妊治療は、最短距離で赤ちゃんを手に入れる方法ではなく、夫婦が向き合い、選び、進んでいくプロセスだと思いました。