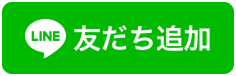保険適用の拡大は不妊治療をどう変えたか
2022年4月、日本で初めて体外受精や顕微授精といった不妊治療までが保険適用になりました。
それまで自由診療で行われていた体外受精は、1回あたり40〜80万円という高額な費用がかかります。
そのため、経済的な理由で治療を諦めざるを得ないご夫婦も少なくありませんでした。
しかし、保険適用の拡大によって、不妊治療は「特別な医療」から「身近な医療」へと大きく変化しました。
ある患者さんから、こんなメールをいただきました。
-
「私たちのような所得の低い夫婦にとって、体外受精は雲の上の医療でした。
今回、保険適用になって、体外受精は手を伸ばせば届く医療になりました。
主人に問題があった私たちでしたが、体外受精という医療のおかげで妊娠することができました。
この巡り合わせに心から感謝しています」
このような声が示すように、保険適用の「光」は確かに存在します。
経済的なハードルが下がったことで、より多くのカップルがチャンスを得られるようになったのです。
体外受精のハードルが下がった
保険適用の最大の恩恵は、なんといっても経済的負担の軽減です。
これまで1回あたり40〜80万円(100万円以上のところも多い)かかった体外受精が、3割負担で20万円前後となり、若い世代のカップルでも選択しやすくなりました。
特に、男性側の精子に問題がある場合や、卵管が閉塞している場合など、「自然妊娠が難しい」ケースでも、体外受精を早期に受けられることは大きな福音です。
また、社会的にも「不妊治療=特別なこと」というイメージが薄れ、オープンに話せるようになってきました。
医療の側から見ても、患者さんが早期に受診し、検査・治療へと進める流れができたのはとても良い傾向です。
保険適用によって、「経済的格差が妊娠のチャンスを左右する」という不公平が減りました。
この意味で、保険適用の「光」はとても大きなものです。
体外受精への誘導と、見えにくくなった「心と体の準備」
しかし、その光の裏側には、見逃せない大きな「影」が広がっています。
第一に、保険診療の報酬制度の問題です。
保険で定められた体外受精の診療報酬は、自由診療時代より大幅に低く設定されました。
そのため、医療機関としては「タイミング法、人工授精によるサポートより、効率の良い体外受精を勧める方が経営的に安定する」という構造が生まれてしまったのです。
結果として、年齢や原因を問わず、「体外受精をおこないましょう」と勧められるケースが増えています。
その流れの中で、「まだ体を整える段階ではないか」「心の準備はできているか」といった大切なプロセスが軽視されているように感じます。
実際、「不妊ルーム」では「体外受精までしたのに妊娠できませんでした」という相談が非常に増えています。
その多くは、検査も治療も適切に行われず、なおかつ「夫婦の心身が妊娠を受け入れる準備が整っていなかった」ケースです。
いまや不妊治療は、適用基準はないがしろにされ、東京などでは体外受精直行便となっています。
若年層の「早すぎる体外受精」
もう一つの影は、30代はもとより、20代女性の体外受精相談が急増していることです。
本来、20代であれば多くの女性は自然妊娠が可能です。
にもかかわらず、「保険で安く受けられるなら」とカップルが考え、また医療機関側も「体外受精ならすぐにお母さんになれますよ」と勧めています。
こうした医療環境のなかで、早い段階で体外受精を選ぶケースが激増しています。
もちろん、適応のあるケース(卵管閉塞や重度の男性不妊など)では、若いうちの体外受精は非常に有効です。
しかし、原因がはっきりしない場合や、軽度の排卵障害、タイミングの問題などであれば、まずは自然妊娠力を回復させる治療を優先すべきです。
若い女性が、まだ自分の体のリズムを理解する前に「人工的な妊娠」を選択することは、時に精神的な負担を大きくします。
体外受精は「最後の手段」ではなくなりましたが、「最初の選択」でもないのです。
この線引きを、私たち医療側が明確に伝えていくことが求められています。
保険適用の時代に求められる「新しい不妊治療の姿」
保険適用によって、不妊治療はより多くの人に開かれた一方で、「誰のための治療か」という原点が見えにくくなっているように感じます。
「不妊ルーム」では、体外受精にエントリーしているカップルでも、それ以外の方法で妊娠できると判断した場合には、「ステップダウン」「マインドリセット」「クールダウン」などのアドバイスをすることが多くあります。
“「体外受精ワールド」だけが妊娠に至る道ではない”ことを示したいという思いが、私にはあります。
自然妊娠、体外受精を問わず、妊娠できるかどうかは、卵巣の中に良い卵子が育つかどうかにかかっているのです。
「卵巣をいたわることから考えてみませんか」というアドバイスをしばしばします。
これからの不妊治療は、「体外受精ありき」ではなく、「その人にとって最適なタイミング・方法・支え方は何か」を一緒に考える時代に移行していかなければなりません。
保険適用という制度は、目的ではなく「手段」にすぎません。
その手段をうまく使うには、なによりもカップルがイニシアティブをもって、医療機関との信頼関係を築くことです。
おわりに
保険適用によって、不妊治療は確かに多くの人の希望を広げました。
一方で、制度の枠組みの中では見落とされやすい「心のケア」や「自然な力の回復」は、それ以上に大切なことです。
不妊治療は、医療技術だけで完結するものではありません。
それは、カップルの人生の一部であり、希望と葛藤の両方を含む「人間の物語」そのものです。
保険診療の時代だからこそ、私たち医療者は、「技術に偏らず、人を診る」姿勢を改めて大切にしていく必要があります。