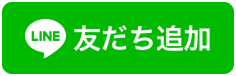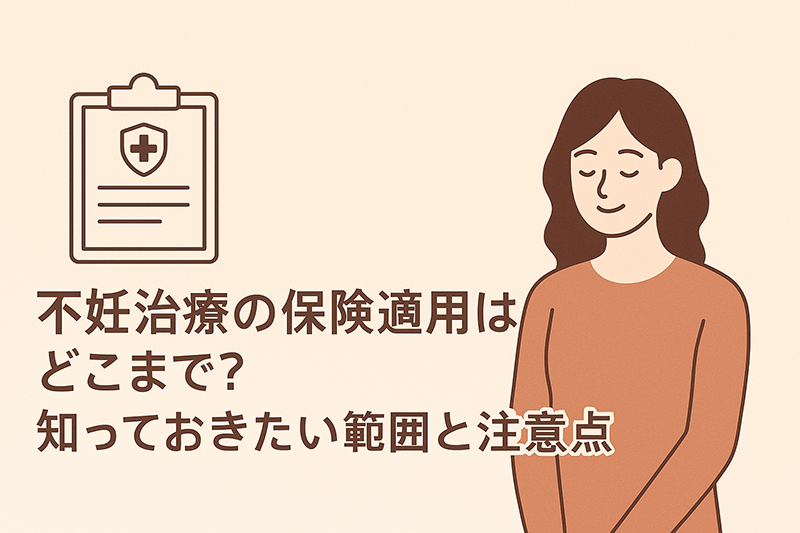不妊治療の保険適用はどこまで?知っておきたい範囲と注意点
「不妊治療って高額そう…」「保険が使えるって聞いたけど、実際どこまで?」
そんな疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。以前はすべて自費診療だった不妊治療ですが、2022年4月から保険適用の範囲が大きく広がり、ぐっと受けやすくなりました。
とはいえ、すべての治療が保険でカバーされるわけではなく、注意が必要な点もあります。この記事では、不妊治療で保険が使える範囲と、事前に知っておきたいポイントをやさしく解説します。
2022年4月、不妊治療に保険が使えるようになりました
少子化が社会的な課題となっている今、妊娠を望むご夫婦を支援するために、不妊治療に対する保険の適用がスタートしました。
これまでは全額自費となり、1回の治療に数十万円かかることも。金銭的な負担が原因で治療を断念せざるを得ない方も少なくありませんでした。
保険が適用されることで費用の負担が軽減され、治療への第一歩が踏み出しやすくなったのはもちろん、治療に関するデータを蓄積しやすくなるという側面もあります。
また「保険が使える=医療として認められている」という意識が社会に広がることで、仕事との両立や周囲の理解が得られやすくなることも期待されています。
不妊治療前の検査も、保険でカバーされます
不妊の原因を調べる初期検査は、以前から保険が適用されています。不妊には、「女性側の要因」「男性側の要因」「原因不明」の3つのタイプがあり、まずは適切な検査で原因を見つけることが大切です。
主な検査内容
- 女性の検査(スクリーニング検査)
- 内診・超音波検査:子宮や卵巣の状態を確認
- ヒューナーテスト(性交後試験):精子が子宮に届いているかを調べる
- 血液検査:ホルモンバランスを確認(FSH、LH、エストロゲン、プロラクチンなど)
- 男性の検査
- 精液検査:精子の数、運動率、形態を調べる
- ホルモン検査:男性ホルモンや性腺刺激ホルモンを血液検査で確認
- 共通の検査
- 卵管造影検査(HSG):卵管が通っているか、癒着していないかを確認
他院で受けた検査結果が有効な場合は、再検査が不要になることもあります。
保険が適用される主な不妊治療とは?
2022年4月以降、以下の治療が保険適用の対象となりました。※治療費とは別に、諸費用がかかる場合もあります。
- タイミング法(タイミング指導)
排卵のタイミングを予測し、妊娠しやすい日を医師がアドバイスする方法。身体への負担が少なく自然に近い妊娠を目指せます。 - 人工授精(AIH)
採取した精子を排卵のタイミングにあわせて子宮内に注入する方法で、妊娠確率を高めます。 - 体外受精(IVF)
卵子と精子を体外で受精させ、受精卵を子宮に戻す治療。自然な受精を促す「ふりかけ法」が対象です。 - 顕微授精(ICSI)
精子を1匹選んで卵子に直接注入する方法。体外受精で受精しない場合に行われます。 - 採卵
卵巣から卵子を採取する処置。経腟超音波ガイド下で行い、麻酔などは別途費用発生の可能性あり。 - 胚培養・胚凍結・胚移植
受精卵(胚)を数日間培養し、状態の良いものを子宮に戻す。余った胚は凍結保存し次回に備える。保管料などが別途発生します。
注意しておきたいポイント
保険適用により選択肢は広がりましたが、以下のようなケースでは保険が使えない場合があります:
- 高グレードな培養液や特殊な技術を希望する場合
- 治療ステップを超える回数を希望する場合(年齢や回数制限あり)
- 自由診療との混合(混合診療不可)
また、保険診療に切り替えたことで治療方針に制限が出るケースもあります。医師と相談しながら、無理のない治療計画を立てましょう。
「安心して治療を受けたい」あなたへ
不妊治療は心も体も、そして時間や費用にも大きな負担がかかります。
それでも「家族を迎えたい」という想いのために、がんばっている方がたくさんいます。
保険適用によって、その一歩が少しでも軽く、前向きになれるようになった今、「わたしにはどんな選択肢があるのか」を知ることは、これからの大きな助けになるはずです。
疑問や不安がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
ひとつひとつ、一緒に整理しながら、安心できる治療の道を見つけていきましょう。