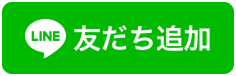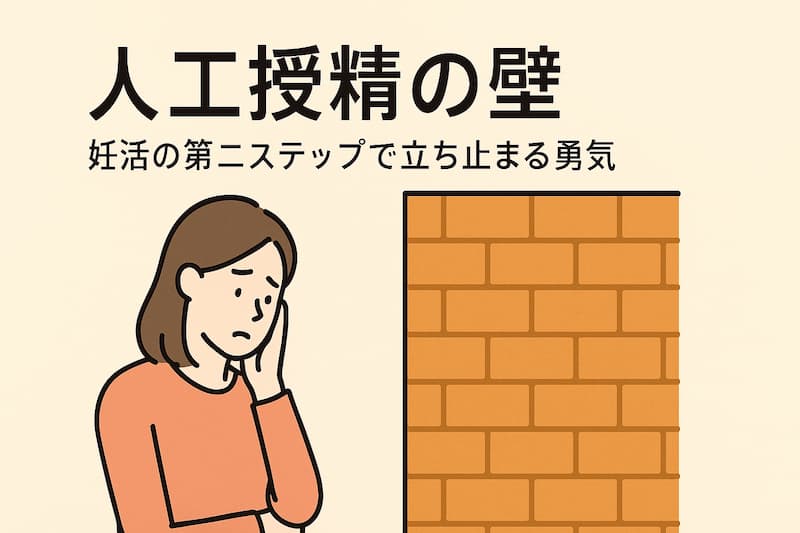1. 妊活のステップアップと「見えない壁」
妊活を始めると、多くの方は次のような流れをたどります。
第一段階はタイミング法。排卵日を予測し、自然に近い形で妊娠を目指す方法です。うまくいかなければ、次は人工授精(AIH)。排卵に合わせて精子を子宮に届けることで、受精のチャンスを少しでも高める方法です。さらに結果が出なければ、第三段階として体外受精(IVF)へ——。
ところが最近、保険適用の拡大や治療の効率化により、この「階段」を一気に駆け上がるケースが増えています。タイミング法をほんの数回試しただけで、すぐ人工授精へ。人工授精も数回、あるいはスルーして体外受精に進む…。
その背景には「時間を無駄にしたくない」という切実な思いがあります。しかし、このスピード感の中で、実は人工授精には見えない“壁”があることを、ぜひ知っていただきたいのです。
2. 人工授精の妊娠率はなぜ低い?
人工授精は、自然妊娠と体外受精の中間に位置する医療です。精子を子宮に届けることで、受精までの距離を縮める——このシンプルなアシストが人工授精です。ところが、その妊娠率は1回あたり5〜8%と、低い数字です。
人工授精は「精子を子宮に届ける」だけで、卵子と精子が出会うのはあくまで体内です。つまり、精子の運動能力や卵管の通過性、受精卵の着床力といった自然のプロセスに大きく依存しています。これが、人工授精の妊娠率が低い理由と考えられます。
しかし、人工授精の妊娠率が低いのは、こうした精子、卵子だけの理由ではありません。妊娠にはオキシトシンというホルモンがとても重要な働きをします。ところが、人工授精は機械的に行われるため、女性の脳からオキシトシンが分泌されることがほとんどないのです。このことも人工授精の妊娠率が低い大きな理由です。ここにも、人工授精の“壁”があります。
3. 踏みとどまる?それとも進む?
人工授精で結果が出ないと、次の選択肢として体外受精(IVF)が浮かびます。確かに、体外受精に進めば「受精できるか」「胚は育つか」といった疑問に答えられるため、原因が見えてくるケースも多いです。
そして、こう考える方が大半です。
「人工授精でダメだったなら、もう自然妊娠も望めないのでは…?」
いいえ、そんなことはありません。人工授精で妊娠しなかったことは、「自然妊娠できない」理由にはなりません。なぜなら、人工授精で妊娠しなかった方の中から、治療をやめた後に自然妊娠する女性が少なくないからです。
「不妊ルーム」で妊娠された方の7割は、不妊治療を経験された方です。その中には、人工授精を何度も受けた方や、体外受精を繰り返した方もいます。ところが、そうした方が「不妊ルーム」というベースキャンプで妊娠されるケースが多いのです。つまり、人工授精での“不成功”は、あなたの妊娠力を否定するものではありません。ここに〝ステップダウン〟という選択肢があるのです。
4. 人工授精の壁で考えてほしいこと
人工授精を続けるべきか、体外受精に進むべきか。この判断はとても難しいものです。ですが、決断を急ぐ前に、次の3つの視点を持ってください。
(1)年齢と時間
年齢は妊娠率に関係します。35歳を超えると、卵子の質が低下してきます。人工授精を続ける時間的余裕がどれくらいあるのか、自分と向き合う必要があります。
(2)体への負担と心の余裕
体外受精は、確かに20%前後の妊娠率を期待できますが、排卵誘発剤、採卵など体への負担が大きく、心身ともに疲弊します。「今の自分にその準備ができているか」も重要です。仕事を持っている女性の中には、体外受精にエントリーしてみたものの、とてもじゃないが時間的・精神的に続けられないと〝ステップダウン〟した方も多くいます。
(3)治療以外の選択肢
意外かもしれませんが、治療から離れることで、体と心のバランスが整い、妊娠力が回復することが少なくありません。特に、ストレスと妊娠に関わる種々のホルモン、神経伝達物質は影響しあうため、精神的な安定は妊娠の大きな味方になります。
5. 「不妊ルーム」で目指すこと
「不妊ルーム」では、妊娠だけをゴールにしていません。妊娠に至るプロセスとしての「妊娠しやすい心と体の土台づくり」を重要視しています。
オキシトシンを増やす生活習慣、食事や睡眠の質改善、体のめぐりを整えるケア…。そして、「卵巣セラピー」で良好な卵子が育つ環境を整える。こうした積み重ねが、妊娠の可能性を高めます。
人工授精の“壁”で立ち止まったとき、それは決して「終わり」ではありません。むしろ、妊活の原点に立ち返る大切なタイミングと考えましょう。
「今、自分にできることは何だろう?」
「治療だけに頼らず、もっと総合的に妊娠力を高める方法はないだろうか?」
そんな視点を持つことが、あなたの妊活を大きく変えるかもしれません。